単純なものほどよく分かっていない・・・。ガスケットとパッキンについてもそうではないでしょうか?ガスケットは固定用、パッキンは摺動用などということは他サイトさんを検索するとすぐ出てくると思います。
ガスケットとパッキンは両方ともシールと呼ばれています。シールについて、一度全体的なものを整理したいと思いました。
機械設計の視点から、マニアックな情報をすこーしだけ掘っていくように解説して、別の機会でさらに深堀して行きたいと思います。
なお、本記事ではJIS B 0116から引用しているものを「○○○○○○○○」で表すこととします。
シールとは モレを止めるモノの総称

シールは「液体の漏れ又は外部からの異物の侵入を防止する機能又は部品」という定義です。
単純にいうと、モレを防ぐ物ですかね。
このシールの種類の中にパッキン、ガスケット、その他の3種類があります。
液体を扱う仕事を行う場合はどれも重要になります。
分類方法 大きくは2種類です
どのように分類されるか、主にはパッキンとガスケットです。定義を見ていきましょう。
パッキンは「回転運動、往復運動などの運動部に用いるシールの総称。運動用シール又は動的シールともいう。注記 一般にはシールと同じ意味を表す。」です。
ガスケットは「フランジ継手などの静止部分(ドアのような開閉部を含む。)に用いるシールの総称。固定用シール又は静的シールともいう。」です。
上記の定義によると、パッキンかガスケットか、どちらで呼べばいいかについては、シールしている部分に於いて、モレを塞ぐ場所が動いているとパッキン、止まっているとガスケットと呼ぶようですね。
ただ、この呼び方、現場の方々でもあまり気にしていません。
例えば、2枚のフランジの間に使うシールは本来「ガスケット」と呼ばなければいけませんが、「フランジパッキン」という呼び名でも通じてしまいます。
「フランジガスケット」が正しい呼び名だ!と揚げ足を取られて注意されても笑顔で「失礼しました」でオッケーです。みんな気にしていませんし、通じるので、さらっと流しましょう。
その他、この二つに当てはまらないものがいくつかあります。
まとめて「その他」に分類していますが、ベローズ、ダイヤフラムなど、重要なものもあります。
主なシール 分類的にはどれか?

ここでは私が普段取り扱っているシールを紹介していきます。概要と分類について述べ、ワンポイントを付けます。
ノンアスジョイントシート ガスケットです
ノンアスジョイントシートは造語になります。ノンアス+ジョイントシートですね。
ノンアスはノンアスベストの略。アスベストを使っていないという意味です。
ジョイントシートは「繊維、ゴム、充填剤などを混練りし、熱ロール上で巻き重ねて作ったシート」。おそらく色々なものを混ぜるところからジョイントってついたのでしょうか?
以前、ガスケットはアスベストを使用していれば大丈夫でしたが、みなさんご存知の通り人体への影響があることから使用できなくなりました。
この出来事はガスケット業界にとってはかなり大きい出来事だったはずです。
アスベスト、高温でも使えて比較的なんでも止められたのに、残念でした。
渦巻きガスケット ガスケットです
正式には「うず巻形ガスケット」というそうです。「テープ状のV字形金属薄板(フープ)と膨張黒鉛テープなどの軟質テープ(フィラー)とを巻重ね、リング状に整形したガスケット」という定義ですね。
特徴はジョイントシートでは無理な条件、主に高圧、高温なものを受け持ちます。
性能は良いのですが、ちょっとでもズレて取り付けたりするとすぐ漏れます。取り扱いをキチンと学習しておく必要があり、少々厄介なガスケット。あとやたら高い。
Oリング パッキンでもガスケットでも使います
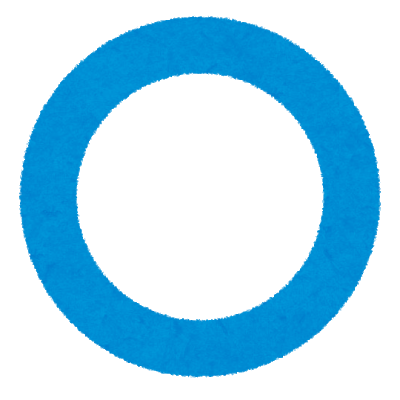
Oリングの定義は「断面形状がO字形(円形)をしたスクィーズパッキン。ガスケットとしても用いる」とあります。スクィーズパッキンとは「Oリング、角リングなどのように、つぶし代を与えて使用する成形パッキンの総称。」とのことです。
パッキンでも、ガスケットでも使うということはどういうことか?
シールする場所が摺動するシリンダーなどではパッキンと呼べます。
圧力容器の蓋等、シールする場所が動かない場所はガスケットと呼べます。
オールマイティですね!
ただ、摺動用、つまりパッキンとして使う場合、Oリングの太さは大きいものを使うことが多いようです。
弱点としては、標準品は寸法が限定されていること(種類は豊富)、温度や液性によって材質を使い分ける必要があり、特殊なものは大体高いこと、基本時に専用の溝を部品に加工する必要がある、等でしょうか。
グランドパッキン パッキンです 軸シールに分類
グランドパッキンの定義は「断面が角形又は円形のスタッフィングボックスに詰め込んで用いるパッキンの総称。」です。スタッフィングボックスとは「グランドパッキン、Vパッキンなどを入れるパッキン箱(又は室)」と定義されます。
この説明だけだとなんのこっちゃわからない人もいるかもしれません。
グランドパッキンは回転している軸(シャフト)の部分に使うシールです。四角い紐のようなもの(グランドパッキン)をシャフトとケーシングの隙間に巻きつけるようにセットして、どんどん詰め込んでいきます。その隙間のことをスタッフィングボックスと呼びます。
なぜ、軸(シャフト)をシールする必要があるか?
軸(シャフト)のシール技術は主にポンプが関わっています。ポンプはモーターを使って軸を回し、何かしら液体を送り出すことが多いです。ポンプは流体を扱うことが多いですから、軸(シャフト)周りから流体のモレを防ぐ技術が必要になってきたというわけです。この軸部分からのモレを防ぐことを軸封といいます。
グランドパッキンは最も古典的な軸シールですね。軸シールとは「軸封部に用いるパッキンの総称。」です。要は隙間になんか適当に詰めてみたって感じ。
難しい用語が多くなってきたので、この辺で。
オイルシール パッキンです これも軸シール

オイルシールの定義は「リップを用いてラジアル方向に締め付け、回転又は往復運動部分のシールを行うリップパッキン。」です。リップとは「軸を抱き密封を行う、通常、エラストマーでできた舌状のシール部分。」です。
これもなんのこっちゃって感じですね。
このシールは軸(シャフト)の外周部をゴムで締め付けられるようにうまく整形したもの、という説明がいいでしょうか。おそらく、ベストな整形を検討した結果、舌状になったということでしょう。
グランドパッキンに比べて構造が単純で扱いも良いのですが、シャフトを抱く、つまり強くシャフトを締め付けるので、シャフトの仕上げなどもしっかりしないといけません。高い圧力も苦手気味。
メカニカルシール パッキンですが、奥が深いし闇も深いです
メカニカルシールは軸シールとしては非常に有名です。定義は「端面シールの一種で、緩衝機構を持つ動的シールユニット。」でJIS B 2405参照となっています。
これは初めてみる方は実物を見てもなんのこっちゃわからないと思います。
簡単にいうと、軸(シャフト)とケーシングにそれぞれ硬くてツルツルしている円盤を取り付け、お互いをバネで押しつけて流体が漏れないようにしている機構のことです。
この円盤がシールの役割を担い、ケーシング側の円盤は固定されていますが、軸側の円盤は回転している、つまり動いているので、シールの分類的にはパッキンとなります。
聞いた感じ、シンプルな構造であるように聞こえますが、気にすべき項目が大変多いです。
円盤の材質、押し付けるバネの形状、軸やケーシングへの取り付け方法、2つのメカニカルシールを使う方法・・・
広がりすぎて、エライ事になっています。こだわればこだわるほど値段も高くなって行き、構造も複雑化します。
厄介なのは、どこまで探求したとしても、メカニカルシールは必ず漏れるということ。
結局円盤を擦り合わせているだけなので、流体はほんのわずかかもしれませんが漏れてしまうんですよね・・・。
ノンシール 最強のように見えて欠陥だらけ
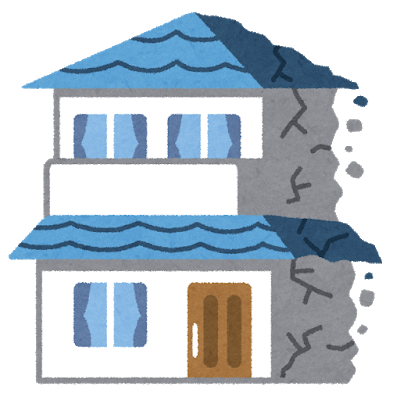
比較的新しい技術として、軸シールがなくても動力を伝えることができるノンシールというものがあります。
一つはモーターごとポンプの中に組み込んで、全て覆ってしまう方法。
もう一つは強力な磁石をシャフトにセットし、磁力の力で触れることなく動力を伝えてポンプを完全密閉する方法です。
シールの部分自体がなくなっているので、漏れないし最強!
かと思いきや、問題は山積みです。
コストが非常に高い。流体に配管の鉄粉などの磁気が帯びてしまうものが混ざっていると故障の原因になりやすい。大きな軸動力が出しにくい。などなど・・・
普段の軸シールと異なる問題が多数想定されますが、限定された用途に使用する分には、ポンプ自体が密閉されますので、軸封部からのモレはよほどのことがない限り起きません。よって信頼性は上がります。
まとめ
上のものをガンガン深堀していきます。
流体を扱う仕事をしている方は一度JIS B 0116に目を通してみてください!
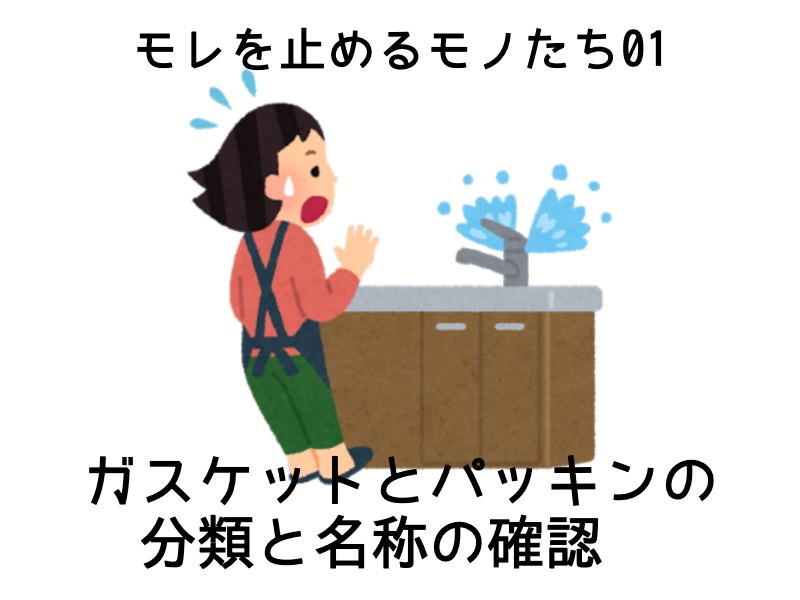

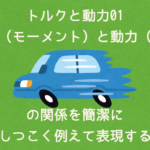
コメント