「図面は加工者への手紙や!」と教えられてきました。JISには加工者への指示がわかりやすくなるようにいろいろルールが設定されています。ここでは、ちょっと「あれ?」と思ったJISのルールについて自分用の忘備録のように記録していきたいと思います。
けっしてJISのルールがすべてではく、ルールから逸脱した方がわかりやすい場面もきっとあります。ただ、ルールは知ってから破るものと思います。
今回は距離に公差を入れてはいけない、という話です。
「距離」に寸法公差を入れてはダメ

例えば、穴と穴の中心間「距離」、2つの面の段差の「距離」等、距離に対してプラスマイナス○○とやってはいけません。
昔の人(私)は「ええ!」となります。でもダメなんです。JISには下記のように書いてあります。
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8114によるほか,次による。
注記 長さに関わる[長さの単位(mm)をもつ]“寸法”には,“サイズ”及び“距離”の2種類がある。この規格で使う前者の“サイズ”とは,サイズ形体の大きさ,すなわち,円・円筒の直径,相対する平行二平面の幅などのことであり,サイズ公差による規制が可能である。後者の“距離”には,例えば,穴の中心間距離,段差の距離などがあり,幾何公差による規制が可能である。JIS B 0401-1,JIS B 0420-1,ISO 14405-2及びISO 14405-3を参照。
出典:JIS B 0001 : 2019
これはここ最近改訂されたJISです。
寸法は「サイズ」と「距離」の2種類ある
私は寸法に種類がある、などどいう感覚はありませんでした。しかし、JISではこのように書かれています。いわれてみれば、実際の長さを持った「サイズ」と、実際にはないけどどれだけ離れているかの「距離」を両方とも寸法と言っていました。これからは「サイズ」と「距離」を別々に考える必要がありそうです。
「距離」寸法に公差はダメというのはJIS B 0420-2:2020がわかりやすい
詳しくはhttps://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.htmlのページからJIS B 0420-2で検索です。
「曖昧さ」が残るので✖とのことです。
距離に公差を入れるときは幾何公差で入れる
では、何で公差を入れるかというと幾何公差で入れるとのことです。幾何公差を使うと、JIS B 0420-2:2020で言われているように、曖昧さを排除できます。
幾何公差はこういうものがはっきりしてくるので便利ですよね。たしかに機械設計者の意図は伝わるし、JISのやろうとしていることはとってもわかるのですが、幾何公差を現場でちゃんと測るのはまだまだ大変だと思うのです。製造業大丈夫かなぁと思います。
幾何公差の測定には課題が多いことは他の記事でもガンガン触れていきたいと思います!
三次元スキャナや測定機が低価格化してきているので、そのうち当たり前になるといいですね。
まとめ
距離は幾何公差で表そう!
でも、ちゃんと測定できるか考えた方がいい!
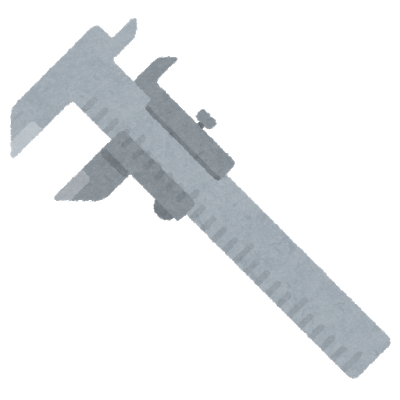


コメント