よく聞く単位系の話、たまに混乱します。今回、自分の忘備録として整理しました。
単位系については歴史的背景などありますが、とりあえず国際単位系 SIをざっくり素早く理解できるようにまとめてみます。
国際単位系 SIを理解するとその他の単位系も理解しやすいです。
- 単位系についてボヤッとしている人
- SI MKS CGS 単位について違いを確認したい人
SIとは何か? : 国際単位系です。グローバルスタンダード!
まずSIとは何か?これはフランス語だそうで「Système International d’unités」の頭文字を取ったものだそうです。この訳が「国際単位系」となります。
なので、「SI単位系」という表現は、「頭の頭痛が痛い」と言っているのと同じで重なり表現になりますので正しくありません。しかし、「SI単位」であれば、SIで規定されている単位、という意味になるので、使用できそうですね。
1960年に国際度量衡総会というところで採択されたそうです。
そもそも単位系とは何か? 単位をまとめたものらしいです。
単位系とは「単位の体系」ということで、色々な単位を集めたものをまとめて単位系と呼ぶそうです。MKS単位系、CGS単位系はもうしばらくしたら解説しますので、少しお待ちください。
ちなみにMKSやCGSには「単位系」をつけます。アルファベット+単位系ですので、SIはつけてはいけないのに、つけていいのかなーという不安な気持ちはわかります。
私も今の今までSI単位系と言っていましたから・・・。機械設計者の皆様、教わらなかったことは常識だそうです。
SIにはまず基本単位がある 7つあるよ!

SIには基本単位と呼ばれる単位が7つあります。基本単位とは、国際的にある基準によって決められた定数を1(いち)として決めた単位、とでも言いますかね。
例えばメートルの定義は
「メートル(記号は m)は長さの SI 単位であり、真空中の光の速さ c を単位 m s−1 で表したときに、その数値を 299 792 458 と定めることによって定義される。ここで、秒は∆νCs によって定義される。」です。
ちなみに∆νCsとは
「セシウム 133 原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数 ∆νCs は、9 192 631 770 Hz」です。
なんでこんな複雑なことになってしまっているのか・・・
昔は「1メートルはこれ!」という見本がありました。メートル原器というそうです。
メートル原器は、その材料や保存方法、温度管理をしっかりして、世界中の基準として運用されていたようなのですが、どうしても時間が経つと長さが変わってしまうそうなのです。基準としてはこれでは困りますよね。
ですので、現在(メートルは1960年以降)は普遍的な定数を実現可能な物理現象を用いて定義化させているとのことです。1メートルは真空中の光の速さとセシウムの何ちゃら周波数から定義されているようですね!
ここに7つの基本単位と何から決められているかだけ載せておきます。
| 量 | 名称 | 記号 | 定義の一部 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 秒 | $$s$$ | セシウムの超微量遷移周波数 |
| 長さ | メートル | $$m$$ | 光の速さ セシウムの超微量遷移周波数 |
| 質量 | キログラム | $$kg$$ | プランク定数 光の速さ セシウムの超微量遷移周波数 |
| 電流 | アンペア | $$A$$ | 電気素量 セシウムの超微量遷移周波数 |
| 熱力学温度 | ケルビン | $$K$$ | ボルツマン定数 プランク定数 光の速さ セシウムの超微量遷移周波数 |
| 物理量 | モル | $$mol$$ | アボガドロ数 |
| 光度 | カンデラ | $$cd$$ | 540 x 1012 Hzの単色放射の視覚効果度 プランク定数 光の速さ セシウムの超微量遷移周波数 |
基本単位を組み合わせた組立単位もある

上記の基本単位を組み合わせて使用する場合もありますので、紹介します。
基本単位を組み合わせて表現した単位を組立単位と呼びます。
代表的な組立単位 見知ったものばかりですね!
ここでは力学における代表的なものを紹介します。こちらの資料から抜粋しました。
| 組立量 | 量の典型的な記号 | 基本単位のみによる表現 |
|---|---|---|
| 面積 | $$A$$ | $$m^{2}$$ |
| 体積 | $$V$$ | $$m^{3}$$ |
| 速さ、速度 | $$v$$ | $$m \ s^{-1}$$ |
| 加速度 | $$a$$ | $$m \ s^{-2}$$ |
この事例を見ればどのようなものが組立単位と呼べるか、わかると思います!
このほかにも組立単位はたくさんあります。
固有の名称と記号を持つ 22 個の SI 単位 組立単位だけど名前があります!
SI単位の中には組立単位だけど、独自に名前を持つものが22個あります。
力学系の単位のみですが下記に少し紹介します。これもこの資料から抜粋していますので、興味がある方はクリックしてみてください。
| 組立量 | 単位の固有の名称 | 基本単位のみによる表現 | 他の SI 単位も用いた表現 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | ヘルツ | $$Hz = s^{-1}$$ | |
| 力 | ニュートン | $$N = kg \ m \ s^{−2}$$ | |
| 圧力、応力 | パスカル | $$Pa = kg \ m^{−1} \ s^{−2}$$ | |
| エネルギー 熱量、仕事 | ジュール | $$J = kg \ m^{2} \ s^{−2}$$ | $$N \ m$$ |
10の○○乗の呼び方 (10進の倍量及び分量)
基本単位や組立単位に比べて、表したい数字がとても大きかったり、逆にとても小さかったりする場合があります。
例えばメートルという基本単位を使って人間の足の大きさを表すのはちょっと不便です。この場合はメートルを使わずにセンチメートルを使いますよね?
そのような時に倍量や分量を表す記号を使って表すと便利です。
今でてきた「センチ」のほか、下に示されているような記号がSIには決められています。これも一部になりますが、紹介します。
| 乗数 | 名称 | 記号 | | | 乗数 | 名称 | 記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $$10^{1}$$ | デカ | $$da$$ | | | $$10^{-1}$$ | デシ | $$d$$ |
| $$10^{2}$$ | ヘクト | $$h$$ | | | $$10^{-2}$$ | センチ | $$c$$ |
| $$10^{3}$$ | キロ | $$k$$ | | | $$10^{-3}$$ | ミリ | $$m$$ |
| $$10^{6}$$ | メガ | $$M$$ | | | $$10^{-6}$$ | マイクロ | $$μ$$ |
| $$10^{9}$$ | ギガ | $$G$$ | | | $$10^{-9}$$ | ナノ | $$n$$ |
その他の単位系

その他、よく聞く単位系について、本当に軽くだけ触れます。
採用された年代に注目して、時系列を確認しておくとより理解が深まります。SIが採択されたのは1960年でした。
MKS単位系とは
MKS単位系は、メートル、キログラム、秒(second)の頭文字をとっています。この三つの単位を基本単位として決めた単位系です。
英語表記は MKS system of unitとなるため、MKS単位系として良いでしょう。
先ほど学習した通り、MKSはSIの基本単位の7つに含まれています。SI単位の中から力学の単位だけを抜き出したものです。
歴史はSIより古いです。1889年に国際度量衡局により採択されたそうです。
MKSA単位系とは
MKSA単位系は、先ほどのMKS単位系にアンペアであるAを足したものになります。
これで電気系の単位も扱えるようになりました。
1901年にジョバンニ・ジョルジさんという人が考案した単位系とのことです。
CGS単位系とは
CGS単位系はセンチメートル、グラム、秒(second)の頭文字をとっています。1832年のカール・フリードリヒ・ガウスさんにより発案されたものだそうです。MKS単位よりも古いです。
MKS単位系と比べて小さい単位が基本単位になっていますので、卓上のスケールにあう科学者に好まれたそうです。
私のまわりでよく聞くCGS単位としては粘度のポアズ($P$)と動粘度のストークス($St$)ですね。これらの単位は本当は使えません。
世界トップクラスの偉い人が考えて統一しようと思ったけど無理だったようです
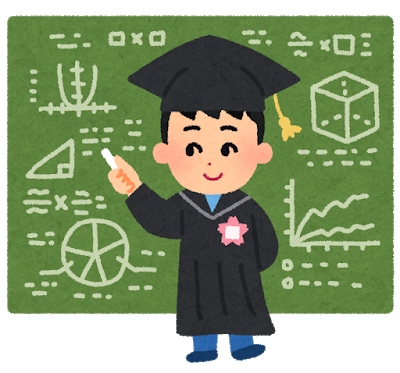
上記で示しましたが、単位系はここ200年で紆余曲折あり現状SIで統一しようということが国際的に提唱されています。
しかし、長年慣れ親しんだ物を手放すことは人間なかなか難しい。
とんでもない頭脳の持ち主たちが一生懸命考えて統一しようと頑張ってくれているみたいなのですが、まだまだまとまっていないのが現状です。最近でも旧式の単位はよく見ますし、換算方法をみんな調べています。
単位換算の注意事項についてはこちらで述べていますので、興味があれば読んでみてください。
SIが採択されてまだ数十年程度ですから、統一されるのはあと100年くらいかかるかもしれませんね。我々が生きている間くらいは我慢して付き合う必要がありそうです。
まとめ
歴史 : CGS ⇨ MKS ⇨ MKSA ⇨ SI
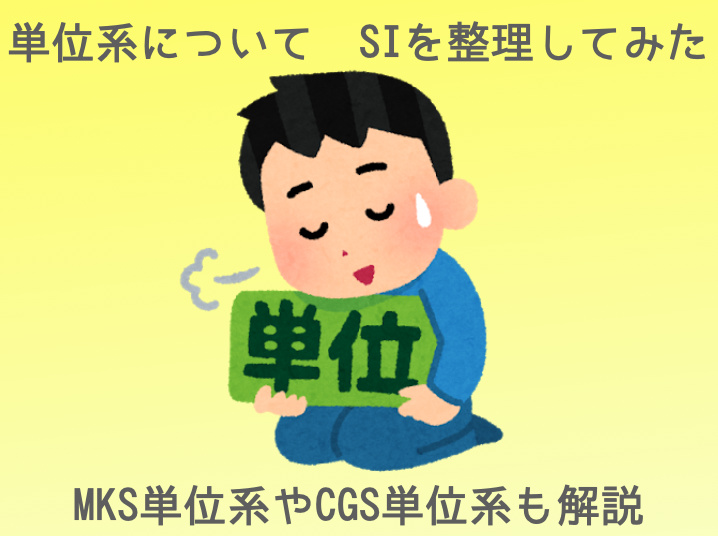
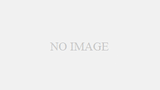
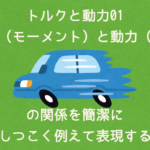
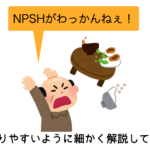
コメント