技術士法は技術士であれば理解必須の事項であると思いますが、
- 漢字が多い
- 長文な割に内容が少ない
- 一文が長く、主語述語が分かりにくい etc
などの要因があり、私が最も苦手とする文章の形体です。法律ですので、抜けがあってはいけないし、ニュアンスが完全に伝わらないと問題なので仕方のないことなのですけれどもね。
そんな技術士法を、技術士法が全くわからない人にとっての導入の意味で、各項目について、簡単にしてみました。ちゃんと勉強したい人は法律本体や参考書をみて欲しいですが、なんとなくーっていう人には少し役に立つと思います。技術士法とは何か、試験勉強を始めたばかりの人にお役に立てるのではないかと思います。
それでは、レッツ技術士法!
全体的な決まり(第一章 総則)

この法律がなぜあるか(目的 第一条)
この法律は技術士の意味を決めることで、技術士の業務を効率化し、科学技術の向上や国民経済の発展を目指すためにあります。イシキタカイナー。
技術士と技術士補とはどんな人?(定義 第二条)
技術士は、科学技術に関係している難しい専門的応用能力が必要なことを「計画」「研究」「設計」「分析」「試験」「評価」する人、または、それらのことを指導する人のことです。技術士補は技術士を補助をする人です。
試験にもこの「計画」「研究」「設計」「分析」「試験」「評価」の6つの項目は大事なようで、自分が今どの業務を行っているかを明確にしておくと良いとのことです。
技術士(又は技術士補)になれない人(欠格条項 第三条)
成年被後見人(精神障害によりしっかりしているときがほとんどない方)又は被保佐人(精神障害により忘れるときがだいぶん増えてきたが、しっかりしているときもある方)は技術士(又は技術士補)になれません。
また、禁錮刑を受けた方や法律違反等により処罰された方等(詳細は略)は2年以上たたないと技術士になれません。詳細は略です。
技術士になるための試験 (第二章 技術士試験)

技術士試験の種類(第四条)
技術士の試験は一次試験と二次試験に分かれており、文部科学省令で決まっているそれぞれの技術の部門ごとに行います。
一次試験に合格すると技術士補になれる資格がもらえ、二次試験に合格すると技術士になれる資格がもらえます。
資格がもらえるだけなので、後から出てくる「登録」をしないと技術士にはなれません。
一次試験の目的 (第一次試験 第五条)
一次試験の目的は以下の資質があるか判断するための試験です。
- 科学技術全般にわたる基礎的学識
- 技術士等の義務(第四章)の遵守の適性
- 技術士補となるのに必要な技術部門の専門的学識
※第一次試験の一部が免除になる資格が、文部科学省令で定められています。
二次試験の目的 (第二次試験 第六条)
二次試験の目的は以下の資質があるか判断するための試験です。
- 技術士となるのに必要な技術部門の専門的学識
- 高等の専門的応用能力
二次試験の受験資格 (第六条 2)
二次試験を受けるには受験資格必要です。受験資格が発生する条件は複数あります。
まず、技術士補として文部科学省令で定める期間以上技術士を補助した時です。
また、第一次試験合格後、職務内容が技術士のものに似ている業務に監督者の元で、文部科学省令で定める期間以上従事している場合も資格を得られます。監督者がいなくてもオッケーですが、期間が異なります。
自分の持っている技術士の技術部門とは別の技術部門の試験を受けるときは、試験の一部免除が可能です。
試験の日程について (技術士試験の執行 第七条)
試験は年1回以上、文部科学大臣が行います
合格証がもらえます (合格証書 第八条)
一次試験または二次試験に合格すると合格証がもらえます。
合格の取り消し (第九条)
不正をすると受験や合格を取り消されます。またそれ以降一定期間試験が受けられなくなることもあります。
受験する時の費用 (受験手数料 第十条)
試験を受ける時は決まった手数料を払わないといけません。手数料は試験運営している期間の収入となります。試験を受けない場合でも手数料は返還されません。
試験を担当する機関の決まり (第十一条〜第三十一条)
文部科学省令により指定された機関(指定試験機関=日本技術士会)が試験を担当してます。指定試験機関になるにはいろいろ決まりがあります。詳細は略。
技術士または技術士補になれる特殊な資格 (第二章の二 技術士等の資格に関する特例 第三十一条の2)
技術士に似ている外国の資格を持っている方(APEC)方はすぐ技術士になれる資格があります。また、JABEE認定教育機関を卒業した方は一次試験が免除になります。
技術士の登録作業 (第三章 技術士等の登録)
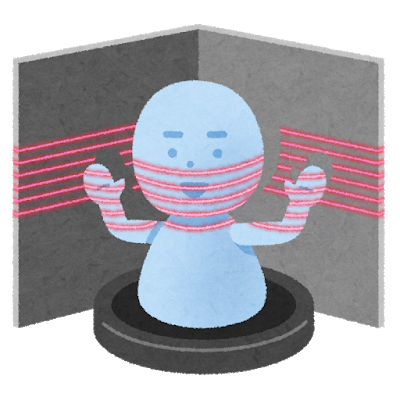
試験に受かったら登録しないと名乗れない (登録 第三十二条)
二次試験に合格したからといって、登録を受けないまま技術士と名乗ってはいけません。技術士補は補佐する技術士も登録必要です。また、技術士補の方が技術士になると技術士補の資格は自動消滅します。
登録関係 (第三十三条〜第三十九条)
登録する内容や名簿のありか、変更方法、手数料などが決められています。詳細は略。
指定登録機関の指定等 準用(第四十条〜第四十三条)
文部科学大臣が指定登録機関を指定すれば業務をお任せできます。今は日本技術士会ですね。第四十二条の準用というところで、指定登録機関(日本技術士会)が登録作業ができるように決まっています。
細々は文部科学省令で定める事になっています。
技術士の義務 (第四章)

ここが一番大事です。箇条書きにしました。
技術士及び技術士補は・・・
- 技術士または技術士補の信用を傷つける行為、不名誉な行為はダメ。(信用失墜行為の禁止 第四十四条)
- 正統理由なく、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりしてはダメ。(技術士等の秘密保持義務 第四十五条)
- 業務では公共の安全、環境の保全、その他公益を害さないようにする。 (技術士等の公益確保の責務 第四十五条の二)
- 技術士の部門の表示は登録した部門だけ。その他はダメ。(技術士の名称表示の場合の義務 第四十六条)
- 技術士補は第二条の業務以外はダメ。(技術士補の業務の制限等 第四十七条)
- 常に業務の知識、技能、その他その資質の向上を図るよう努める。(技術士の資質向上の責務 第四十七条の二)
削除された項目 (第五章 削除 第四十八条〜第五十三条)
法律なので、削除されても「削除された事」が残るようになっています。
日本技術士会の話 (第六章 日本技術士会 第五十四条〜第五十六条)

日本技術士会の目的 (設立 第五十四条)
「日本技術士会」という文字を使用する一般社団法人についての規程があります。ようするに日本技術士会が存在する目的が書いてあると解釈しても良いのではないでしょうか。書かれている事はかっこいいのですが、意識高い系すぎて眩しくて目が潰れそうです。内容は略。
そういう一般社団法人が成立した時の届出方法(成立の届出 第五十五条)
成立したら文部科学大臣に届けるそうです。期間とか添付しないといけない書類もあるとのことです。
業務の管轄 (技術士会の業務の監督 第五十五条の二)
技術士会の業務は文部科学大臣の管轄です。文部科学大臣は技術士会の行う業務に対して検査したり、必要な命令をしたりできます。
その他色々 (第七章 雑則)
お金関係 (業務に対する報酬 第五十六条)
技術士への報酬はちゃんとしてくださいね!というのが決まっています。
技術士や技術士補の名前を使う時 (名称の使用の制限 第五十七条)
技術士や技術士補じゃない方は、技術士や技術士補、又はこれに似ている名称を使用してはダメ。
法律が変わる時の猶予期間 (経過措置 第五十八条)
法律の制定又は改廃をする時、合理的な理由がある場合は、一定期間、新規定をゆるく適用し、新しい秩序への移行を滑らかにする措置をとることができます。
罰則の種類と刑の重さ色々 (第八章 罰則 第五十九条〜第六十四条)
上記規定に違反した時の罰則と罰金が書いてあります。詳細は略。
まとめ
簡単に書いてはみたけど、ちゃんと原文で読むことをオススメします!
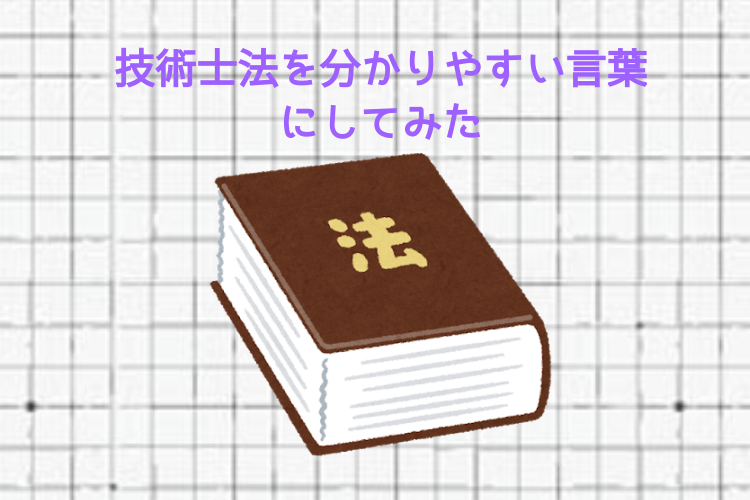


コメント