関数電卓、つかってますか?機械設計の方は業種にもよると思いますが、私はほとんど使いません。関数電卓でできることはPCでも大体できますし、PCであれば記録に残って使い回しも可能になりますので、同じように時間をかけるのであれば関数電卓はあまり使わない方がいいのではないかなぁと思っています。
ですが、出張先や現場でたまーに使うことがあります。
そこで困るのが、誤作動による設定の変更です。カバンから取り出すのに適当に関数電卓をとったら、たまたまボタンを押してしまい、設定が変わってよくわからない数字になっている・・・。
現場や出張先では判断にスピードや正確性が求められます。そのような状況下で関数電卓を使用して手間取っていたら、時間だけではなく信頼までも失いそうです。
そんな状況を簡単に打破できるように次の事をおさえておいたらいいよーっていう忘備録的なものを紹介します。皆さんとシェアしたいとおもいます。
- 関数電卓を滅多に使わない方
- 関数電卓で使われる3文字から4文字の略語をざっと理解したい方
- 実際に操作方法がわからなくなった経験がある方
まずは略語の紹介 この部分だけみればOKな人も多いはず
それではまず関数電卓に使われる略語一覧から確認していきます。

私はシャープ製の関数電卓を使っていますが、カシオなど他のメーカーのものだと少し略語が異なるようです。ですが、共通で理解できるものも多いです!
これだけでオッケーな人は多いはずなので、ご活用下さい。
関数電卓を滅多に使わない方は特に一通り確認しておくことをおすすめします!
| 略語 | 説明 |
|---|---|
| NORMAL | 一般モード。加減乗除算や関数計算を行う。 |
| COMP | compute(計算)の略。 四則演算、関数計算を行うモード。 |
| STAT | statistics(統計学)の略。 統計計算モード。標準偏差や正規分布関数の値を計算できる。 |
| SD | standard deviation (標準偏差)の頭文字。 統計計算モードを指す。 |
| EQN | equation(方程式)のミススペル。 方程式モード。連立方程式や2次、3次方程式を計算できる。 |
| CPLX | complex(複合の)の略。 複素数計算モード。直交座標や極座標で複素数の計算ができる。 |
| DEG | degree(角度)の略。 角度の単位を度(1回転が360°)にする。 |
| RAD | radian(ラジアン、弧度)の略。 角度の単位をラジアン(1回転が2π)にする。 |
| GRAD | grade(グラード)の略。 角度の単位をグラード(1回転が400g)にする。 |
| DRG | 角度単位の上記3種類(DEG, RAD, GRAD)の頭文字を一つずつ取った略称。 |
| FIX | fix(固定する)。 関数電卓では、小数点の位置を固定するという意味。 |
| SCI | scientific notation(科学的表記)の略。 指数表記のこと。 |
| ENG | engineering notation (工学的表記)の略。 指数を3の倍数で表す方法のこと。 |
| FSE | 小数点表記の上記3種類(FIX, SCI, ENG)の頭文字を一つずつ取った略称。 |
| BIN | binary(2の)の略。 2進数のこと。 |
| PEN | pental(5の)の略。 5進数のこと。 |
| OCT | octal(8の)の略。 8進数のこと。 |
| DEC | decimal(10の)の略。 10進数のこと。 |
| HEX | hexadecimal(16の)の略。 16進数のこと。ちなみに6はhexaというので6進数とも読める。紛らわしい。 |
| RCL | recall(思い出す)の略。 メモリーからの呼び出しの意味。 |
| STO | store(記憶)の略。 メモリーへの記憶の意味。 |
よく起きる問題とその対処
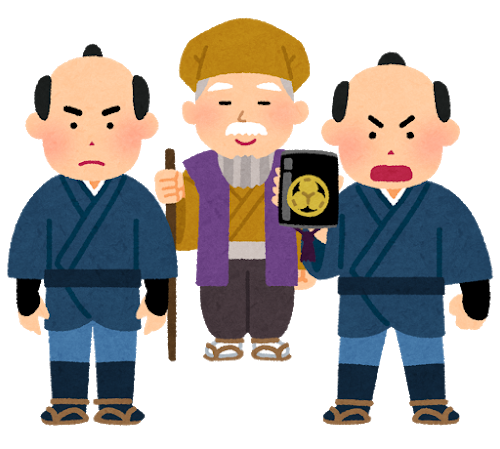
続いては、私がよく遭遇する問題点を挙げていきます。「あーあるある!」的なものがあったら幸いです!
モードについて モード選択ボタンを確認
四則演算で使っていただけなのに、急に「a=?」のような見慣れない表示が出てきたらモードが変わっています。
ほとんどの関数電卓は四則演算、関数計算などが可能な通常計算モードの他に、統計処理(STAT)、方程式計算(EQN)、複素数計算(CPLX)などの機能が搭載されています。計算モードは大体「MODE」ボタンで切り替えます。
見慣れない画面が表示されたら、モード選択用の「MODE」ボタンを探し、「NORMAL」や「COMP」などの通常計算モードに戻しましょう。
関数電卓の角度単位について 「DRG」を確認
関数電卓でサインやコサインを計算しようとした時、「cos 90」と入力したのに答えが1にならない時ありませんでしたか?
関数電卓の角度の種類は複数あります。度数表記のDEG、ラジアン表記のRAD、グラード表記のGRADの3つが有名です。
角度が「°」からいつの間にか「RAD」に変わっていたりするんですよね・・・。
こういう時は設定コマンドから「DRG」という項目を見つけてください。
なんと「DRG」は「DEG」「RAD」「GRAD」の3つの頭文字を取った項目なのです。
設定メニューから「DRG」を見つけてお好きな角度単位にもどしましょう!
指数表記(10の〇〇乗)について 「FSE」を確認
機械設計の方であれば、関数電卓を使用した計算結果を10の〇〇乗という指数の形で表現したくなる場合もあると思います。こういったとき使うのが「FSE」の設定です。
「FSE」とは「FIX」「SCI」「ENG」の3つの頭文字を取った項目です。
SCIとENGはそれぞれ指数の設定ですが、個人的に指数はあまり使いません。使い慣れていない関数電卓で使い慣れていない表示をされると間違いの元だからです。
ですので、10の〇〇乗という表記になってしまったら「FSE」コマンドで「FIX」に戻す、ということをよくやっています。
余談
10の指数を間違えると致命的なので注意が必要です。よろしければこの記事を参照してみてください。
まとめ
関数電卓は使わなくても何ができるか把握しておくと良いですよ!
特に「DRG (DEG, RAD, GRAD)」「FSE (FIX, SCI, ENG)」!
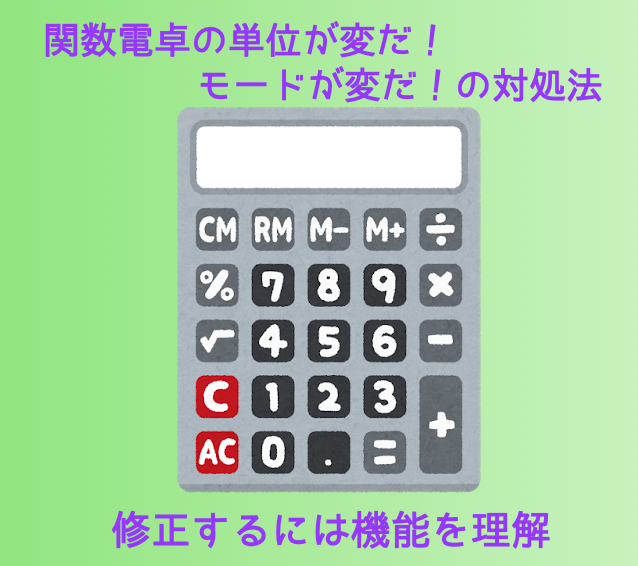
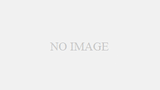
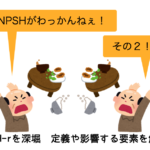

コメント