今回は位置度、輪郭度についてです。私の場合、鋳物や板金の図面を書くことがほとんどないので、輪郭度はほとんど使いません。よって位置度中心の記事になると思います。
位置度はデータムと理論的に正確な寸法を多用します。データムの付け方はこちらを参考にしてください。理論的に正確な寸法を解説し、その後位置度の概念、検証方法、使い方と問題点に触れていきます。
理論的に正確な寸法とは?

文字通り、理論的に正確な寸法のことです。長いですが、正式な呼び名です。ちなみにCADソフトでは「理論的正確」などと略されています。
誤差のない寸法のこと
通常は寸法には誤差があり、寸法ピッタリで製品が出来上がることは絶対にありません。ところが、理論的に正確な寸法は、寸法通りジャストでできていると仮定します。その寸法に幾何公差を記入し、理想からどれだけズレているか、という考え方をします。
現実には存在せず、理想の部品が存在していると仮定することになります。
公差の記入は不要
理論的に正確な寸法は、数字を□で囲って表します。理想の寸法で出来上がっていると仮定するので、寸法公差(サイズ公差)の記入は不要です。
この理想の部品からどれくらいズレているか、を述べるのが位置度や輪郭度です。
位置度とは
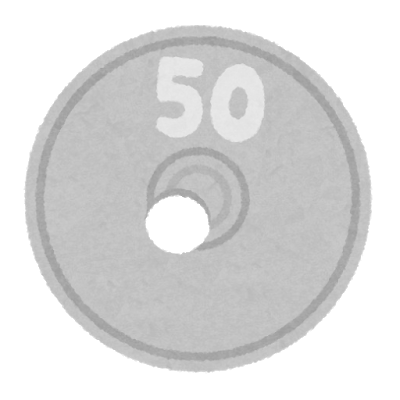
主に穴の位置の正確さを示す
位置度は位置の正確さを示します。記号を見ればイメージできると思いますが、主に穴の位置の正確さが求められる時に使用します。しかし、穴だけではなく、形状全般に幅広く使うことができます。
実は「全般」に使えるけど便利ではない
位置度は位置の正確さですので、例えば、あるデータムからの平行の度合いを表す平行度の代わりにも使うことができます。
全般に使えるので、むしろこれだけでもいいのでは?と思いますが、平行度や直角度の方が直感的にわかりやすいので、図面を見る人にとってわかりやすくなるように、位置度を多用するのは避けた方がいいと思います。
私は主に穴の位置関係の正確さを表すために使用しています。
線(面)の輪郭度とは

(曲)線や(曲)面がどれだけズレているか
(曲)線または(曲)面が、指定された理論的に正確な寸法からどれだけズレているかを表します。
輪郭度も専用の記号がありますが、先ほど述べた通り、位置度で示すこともできます。まっすぐでは無い曲がった線や面を正確に作って欲しい場合は輪郭度を使用した方が良いと思います。まっすぐな場合は平行度や直角度を使った方がわかりやすいです。
NCだと話は別ですが、旋盤やフライス盤を使用した加工ではほとんど使わないと思います。加工自体が平行的、直角的なのもが多いですからね。主に鋳物や板金加工向けに使われるものだと考えています。
位置度や輪郭度に使うデータムについて


データム の有無で意味が変わることに注意
位置度や輪郭度に使うデータムは、必要な場合もあれば、不要な場合もあります。有る場合も無い場合も意味が通ってしまうので、設計者の意図が正確に伝わらない可能性があります。位置度や輪郭度のデータムについては、注意して理解しておく必要があります。
データムが無い場合は相対的な位置関係だけを規制
データムを指定しない位置度や輪郭度は基準がないので、理論的に正確な寸法で示された形状の維持、つまり、理論的に正確な寸法で示された相対的な位置関係だけを規制することとなります。
例えば、四角いプレートに穴が4つ開いている場合を考えます。それらの穴に位置度のの指定があるものの、データムの指定がなく、穴同士の位置関係に「理論的に正確な寸法」が指定されていた場合は、プレートに開けた穴の位置関係さえ合っていれば、4つの穴はプレートのどの位置にあっても問題無し、となります。
検証方法
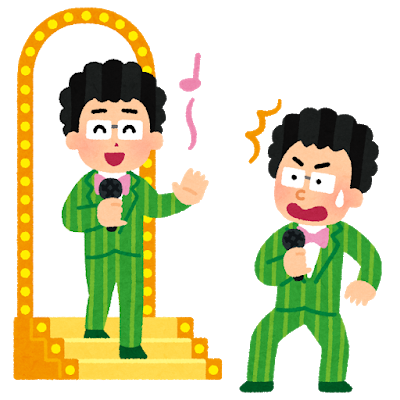
見本を作ってあてがう
検証方法として考えられるのは、ほぼ理論的に正確な寸法でできている見本を作って、測定対象にあてがうことです。
穴の位置度のチェックであれば、プレートを用意し、そのプレートへ測定する穴にしっくり入るようなボスを差し込んだ治具を作って、完成した製品へはめる、という手順となります。
弱点としては、合格か不合格かの判定しかできません。平行度のように、数値としての検査記録を残すことは難しいと思います。
面の場合、あてがったところが凹んでいれば良いのですが、凸であると全ての測定箇所が狂います。ですので、合格しているか否かしかわかりません。
三次元測定器
空間認識といえば、三次元測定機です。位置度や輪郭度の測定は三次元測定機の独壇場と言えるのではないでしょうか。
ただ、測定する範囲はちゃんと決めておかないと、膨大な箇所を測定しないといけなくなるか、十分な測定がされずに不合格品が合格になる可能性があります。太い一点鎖線を使って指定しておくと測定者も測定しやすいと思います。
今後は3Dスキャナにも期待しています。
使い方と問題点
位置度は穴の正確さを表すのに使うが、検証しにくい
私の場合は、主に穴の位置の厳しさを表すのに使っています。例えば、2つの穴へ位置決めピンを挿入し、精度の良い製品の加工をするような厳しい位置出しをするのであれば、当然厳しい公差を与えますし、ボルトナットの締結に使うバカ穴程度であれば緩い公差を指定します。
しかし、検証は大変です。ノギスや定規を当てるのも限界があります。見本を使って、あてがうのは方法の一つですが、どれくらいズレているという数値的な記録は残すことができません。一つ一つの製品全てに専用の検査見本が必要になる上、その検査見本が正しくできているかの管理も必要です。
記録をのこす測定には三次元測定器や3Dスキャナが合理的です。
輪郭度は必要十分な検査ができるよう打ち合わせ必要
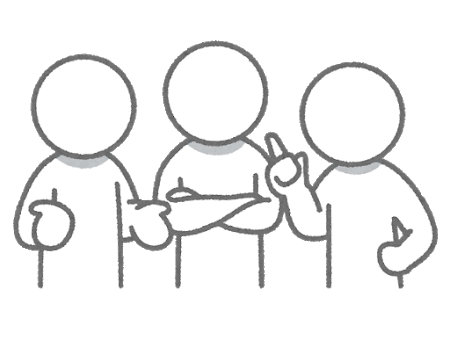
輪郭度はかなり職人色の強い幾何公差だと思います。「測定する」という概念が無い項目だと考えています。輪郭度を指定する際はその検査方法と合否判定の方法について、製造者、検査の方とよく打ち合わせをして不良が無いように注意しましょう。
昔は職人さんが形状を見て触って判断していたのだと思います。位置度や輪郭度は職人さんの合格判定方法と言えます。
まとめ
位置度、輪郭度は色々使えて便利だけど検証が大変!
理論的に正確な寸法を理解して上手く使っていきたい!
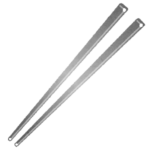

コメント